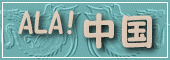|
|  |  |
「天地の中央」にある登封の史跡群は、中華人民共和国の世界遺産の一つである。中華人民共和国(中国)の河南省に聳える嵩山は、古来五岳の中心をなす聖なる山として、宗教的・文化的に重要な位置を占めてきた。この世界遺産は、その嵩山周辺で歴代の王朝時代に築き上げられてきた、嵩山少林寺をはじめとする8件の歴史的建造物群を対象としている。
天地之中
古代中国の宇宙観は「天円地方」、すなわち「天は円く、地は四角い」というもので[2][3]、その天地が巨木や高峰でつながっていると信じられていた。
中国は中華思想に基づき自らを天地の中心に置いていた。その中でも中心に位置するとされたのが中原で、古代の為政者はここに都を置いた。嵩山は「五岳」の中心としてそこに聳え、天地の中心に位置する聖なる山として、古くから仏教、儒教、道教などの宗教的な建造物群が多く作られるとともに、学術・教育に関する施設も形成されてきた
世界遺産を構成する登録資産は、河南省鄭州の登封市に残る以下の8件である。その中がさらに細分化され、構成資産の総数は367にのぼる。
太室闕と中岳廟
太室闕と中岳廟は、嵩山の黄蓋峰の麓に残る道教の廟とその闕で、世界遺産としての登録面積は 372.3 ha、緩衝地域は 496.3 ha である。
太室闕(たいしつけつ)は、後漢時代の西暦118年に建てられた高さ 3.92m の闕である[6]。。後述する少室闕、啓母闕とともに、中岳漢三闕と呼ばれている[6]。中国には他にも古い闕が残っているが、漢代のものがそのまま残っているのは中岳漢三闕しかなく[7]、現存する中国最古の宗教的構造物となっている[3]。こうした背景には、当時の主要建築物が木造で、残りにくかったという事情もある。
太室闕は木造建築物を模してはいるが、切石を積み上げて作られたもので、四面に様々な文物を題材にとった浮き彫りがある。それらが漢代の習俗に関する史料となるだけでなく、複数の書体によって刻まれた銘文は書法の変遷に関わる資料となっている。
太室闕は後述する中岳廟の前身である「太室祠」の外大門となっていた。太室祠は太室山(嵩山の一部)の神を祭るための施設で、古代には重要な意味を持った。道教の廟堂に改築された太室祠と異なり、太室闕は当時の祭礼の例証となるものである。
中岳廟
中岳廟(ちゅうがくびょう)は秦代に創建された「太室祠」が前身になったと伝えられる道教の廟で[9][2]、漢の武帝の時代に大規模な拡張が行われた[10]。道教を大成した寇謙之もこの地で長年修行をしたと伝えられ[2]、彼が生きていた北魏の時代に現在の名になり[10]、唐の時代に現在の場所に移築された[9]。その後も多くの変遷を遂げたが、清代の改築によって現在の規模になった[10][9][7]。清代の改築は故宮を範とするものであったため、「小故宮」とも称された[2]。中岳廟は南北の軸線に沿って天中閣、中岳大殿、寝殿、御書楼などの37の建造物群で構成され[9][7]、河南省に残る宗教建築では最大規模とも言われる[10]。
少室闕
少室闕(しょうしつけつ、Shaoshi Que Gates, 1305-002[5])は、嵩山の少室山の麓に残る中岳漢三闕の一つで[6]、世界遺産としての登録面積は 84 ha、緩衝地域は 222.4 ha である[4]。少室山の神を祀る少室山廟の前に建てられた闕であり、建造時期は118年から123年の間とされている[6]。中岳漢三闕の中では知名度の点で劣るかわりに、それによってかえって壁画が良好に保たれたという評価もある[8]。
描かれている壁画は多岐にわたるが、少女の躍動感がきわだつ馬戯図や女子蹴鞠図などが知られ、後者は漢代にすでに存在していたサッカーのような球技の祖形を伝えている[6][8][7]。
啓母闕
啓母闕(けいぼけつ、Qimu Que Gates, 1305-003[5])は中岳漢三闕の一つで、世界遺産としての登録面積は 40.4 ha、緩衝地域は 108.9 ha である[4]。
嵩山の万歳峰の下に位置し、123年に啓母廟の闕として建てられた。啓母廟は高さ10mにもなる巨石「啓母石」を祀るために建造されたが[6]、現存していない[7]。
『淮南子』に記載された伝説によれば、夏王朝の始祖となった禹は治水事業に打ち込むあまりに家を省みず、そのために妻が巨石に変じたという。のちにその巨石からは夏の2代帝啓が生まれ、そこから「啓母石」の名がついたとされる[8]。こうした経緯は啓母闕の碑文にも部分的に刻まれている[6][8]。啓母闕には様々な銘文や画像が刻まれ、当時の書体や彫刻を考察する上で重要な資料となっている。
嵩岳寺塔
嵩岳寺塔(すうがくじとう、Songye Temple Pagoda, 1305-004[5])は、嵩山の太室山南麓に残る嵩岳寺の仏塔で、中国に現存する煉瓦塔としては最も古い[11][12]。北魏の時代には皇帝の離宮だった建物が520年に仏教寺院とされ、その同じ年に仏塔も建てられた。当初は閑居寺という名だったが、620年に嵩岳寺と改称された。その後、寺そのものは衰退し、現在残るものは清代に再建されたものだが、仏塔は北魏時代のものがそのまま残っている[11]。
高さは約40 m で、密檐式[注釈 3]という、楼閣式を簡略化した様式の塔である[13]。外観の平面は十二角形で、徐々に小さくなる15層の密檐が積み重なり、その上に相輪が載っている[11][12]。内部は十二角形になっている第一層以外は八角形である。
世界遺産としての登録面積は 33.4 ha、緩衝地域は 47.9 ha である[4]。
少林寺建築群
少林寺建築群 (Architectural Complex of Shaolin Temple (Kernel Compound, Chuzu Temple, Pagoda Forest), 1305-005[5]) は、世界遺産の英語登録名にあるように常住院、初祖庵、塔林などを含む少林寺の建造物群で、登録面積は 182.6 ha、緩衝地域は 1939.6 ha である[4]。
少林寺は北魏の孝文帝が跋陀のために命じて、495年に少室山五乳峯に建てさせた仏教寺院で、527年に渡来僧菩提達磨が禅宗を創始してからは禅宗の祖庭として知られるようになった[14][15]。また、達磨が始祖とされる少林拳の使い手である僧侶たちが、唐の太宗を助けて軍功を立てたことから、拳法でも知られるようになった[15]。ただし、少林寺の古い建築物は中華民国時代に焼失したものも少なくない[15]。
常住院に残る建築物で特筆すべきは千仏殿(せんぶつでん)である[16]。これは明代の1588年に建てられたもので、現存する少林寺建築群の中では最大級のものである[15]。清代に再建されたが、内部には明代に描かれた約300 m²の巨大な壁画「五百羅漢朝毘盧」が残っている[15][14]。
初祖庵(しょそあん)は、初祖すなわち菩提達磨が壁に向かって座禅したと伝えられる場所に残る建築群である[15]。ただし、現存するのは1125年に建造された大殿と、清代に追加された小さな建物(小亭)2つなどである[15]。大殿は木造で、河南省に現存する木造建築の中でも傑作のひとつして挙げられている[14]。
塔林(とうりん)は少林寺の僧たちの墓所であり、世界遺産に推薦された時点で241基もの墓塔が林立していた様からその名がある[16]。それらの墓塔は唐代から清代まで13世紀にわたって建てられてきたもので[16]、建築と彫刻の点から高く評価されている[14]。
会善寺
会善寺(かいぜんじ、Huishan Temple, 1305-006[5])は、少林寺、嵩岳寺、法王寺[注釈 4]とともに嵩山の四大寺院の一つである[16]。太室山積翠峰の下にあり、北魏時代の離宮を起源とする[17]。「会善寺」の名は隋の時代に付けられ[17]、現在の建物は元の時代に成立した[16]。明や清の時代に何度も改築されているが、正門をはじめとする8件の構造物には、元朝の様式が残されている[16]。
世界遺産としての登録面積は 68.2 ha、緩衝地域は 373 ha である[4]。
嵩陽書院
嵩陽書院(すうようしょいん、Songyang Academy of Classical Learning, 1305-007[5])は儒教の書院(学問所)で、世界遺産としての登録面積は 27.8 ha、緩衝地域は 115.4 ha である[4]。北魏の時代に建造された嵩陽寺を起源とし、それから何度も改称されたあと、宋の時代に現在の名称となり[18]、当時は儒教を講ずる四大書院の一つに数えられて名を知られていた[16]。宋明理学の基礎をつくったことで知られる程顥・程頤もここで講義したことがある[18][2]。
現存する建物自体は清代のもので、様式は河南省に典型的なものが採用されている[16]。
嵩陽書院は建物そのものだけでなく、周囲にも特筆すべきものがある。ひとつはその素晴らしさから漢の武帝が将軍に列したと伝えられる柏の老木「大将軍」と「二将軍」である。当時は「三将軍」もあったが、これは明代に焼失した[18]。樹齢は4500年とも言われ、中国では最古級の老木である[16]。
もうひとつが門前に聳える高さ8 m の石碑、嵩陽観感応碑(すうようかんかんのうひ)である。これは唐代に当たる744年の建造で、嵩山に残る石碑としては最大で[18]、河南省内でも最大とされる[16]。銘文を手がけたのは高名な書家の徐浩である[18]。
周公測景台と観星台
周公測景台と観星台(Observatory, 1305-008[5][注釈 5])は、中国の科学技術史に関わる施設である。
周公測景台(しゅうこうそくけいだい)は、「測影台」とも表記する[19][2]。その別表記に表れているように影の長さを測るもので、一種の日時計である。伝説的には、周公が天地の中心を定める時に日陰の長さを測ろうと設置したのが最初とされる[2]。現存するものは周公の業績を偲ぶ形で723年に天文学者によって設置されたもので[20][19]、中国の天文観測施設としては現存最古である[19][2]。
観星台(かんせいだい)は、周公測景台のすぐ北に残る天文観測施設で、元代の1279年に、郭守敬によって建てられた[19][注釈 6]。この時代までの現存する天文施設としては最大級で、当初は 9.46 mだったが、明代に上乗せされた部分が3 m 余りある[20]。この天文施設は日陰の長さを元に冬至や夏至のほか、緯度の高さなどを算定するものであった[19]。郭守敬は中国全土に27の観測拠点を置いたが、その中心をなしたのが登封の観星台であった[20][21]。彼は北京の観星台とともに「天地の中心」たる登封の観星台を重視しており、他と違ってその2つだけはレンガ造りになっていた[21]。彼は当時として傑出した暦である授時暦を作成したが、その際には観星台群から得られた観測記録が活用されていた[2][21]。
世界遺産としての登録面積は 16.3 ha、緩衝地域は 134.6 ha である[4]。
|
|
|
|
|  |
|