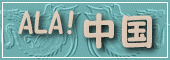|
|  | 雲崗洞窟(うんこうどうくつ)は、山西省大同市の西方20キロにある東西1キロにわたる約40窟の洞窟寺院。
元は霊巌寺といい、現在では石仏寺と呼ばれます。北魏の沙門統である曇曜が文成帝に上奏して460年(和平元年)に、桑乾河の支流の武周川の断崖に開いた所謂「曇曜五窟」に始まります。三武一宗の廃仏の第一回、太武帝の廃仏の後を受けた仏教復興事業のシンボル的存在が、この5座の巨大な石仏でした。
その後、巨大な石窟寺院が15座開かれ、雲崗期(460年-493年)と呼ばれる仏教彫刻史上の一時期を形成しました。
様式上は、最初期の「曇曜五窟」には、ガンダーラやグプタ朝の様式の影響が色濃く、また、ギリシア様式の唐草文様に代表される西方起源の意匠も凝らされています。また、当時の建築様式を模した装飾も豊富に見られます。しかし、486年以降の末期になると、初期の雄大な質感は姿を消し、華奢で力強さの感じられない造形が増加する傾向が顕著となります。そして、この傾向の延長線上に、続く龍門期が待ち受けています。
また、その影響関係で言えば、雲崗の様式は、敦煌莫高窟にその淵源を持ち、また雲崗の影響は、龍門・天龍山・南北の響堂山などの石窟寺院に及んでいます。
[改訂履歴] |
|
|
|
|  |
|