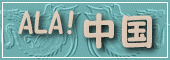|
|  | 龍門洞窟(りゅうもんどうくつ)は、河南省洛陽市の南方13キロ、伊河の両岸にある洞窟寺院。
北魏の孝文帝が山西省の大同から洛陽に遷都した494年(太和18年)に始まります。仏教彫刻史上、雲崗期の後を受けた、龍門期(494年-520年)と呼ばれる時期の始まりです。
龍門石窟の特徴は、その硬さ、すなわち雲崗の粗い砂岩質と比較して、緻密な橄欖岩質であることです。そのため、北魏期においては、雲崗のような巨大な石窟を開削することが技術的にできませんでした。「魏書釈老志」にも、500年(景明2年)に宣武帝が孝文帝のために造営した石窟は、規模が大きすぎて日の目を見ず、計画縮小を余儀なくされた顛末を記しています。
様式上の特徴は、面長でなで肩、首が長い造形であり、全体的に華奢な印象を与える点にあります。また、中国固有の造形も目立つようになり、西方風の意匠は希薄となります。裳掛座が発達して、装飾も繊細で絵画的な表現がされるようになります。
最初期の「古陽洞」周辺に見られる私的な仏龕の造営に始まるが、先述の宣武帝の計画を受けて開削された「賓陽洞」3窟も、実際に完成したのは、唐の初期でした。その他、北魏時期の代表的な石窟としては、「蓮華洞」が見られます。また、北魏滅亡後も石窟の造営は細々とながらも継続され、「薬方洞」は北斉から隋にかけての時期に造営された石窟です。
唐代には、魏王泰が賓陽3洞を修復し、褚遂良に命じて書道史上名高い「伊闕仏龕碑」を書かせ、641年(貞観15年)に建碑しました。初唐の代表は、656年-669年(顕慶年間〜総章年間)に完成した「敬善寺洞」です。その後、「恵簡洞」や「万仏洞」が完成し、この高宗時代に、龍門石窟は最盛期を迎えることとなります。
その絶頂期の石窟が、675年(上元2年)に完成した「奉先寺洞」です。これは、高宗の発願になるもので、皇后の武氏、のちの武則天も浄財を寄進していますが、その本尊、盧舎那仏の顔は、実は当時既に実権を掌握していた武則天の容貌を写し取ったものと言われています。龍門最大の石窟です。
武則天の時代には、西山の南方、「浄土洞」の付近まで造営が及んだので、武則天末より玄宗にかけての時期には、東山にも石窟が開削されるようになりました。「看経寺洞」がその代表です。
[改訂履歴] |
|
|
|
|  |
|